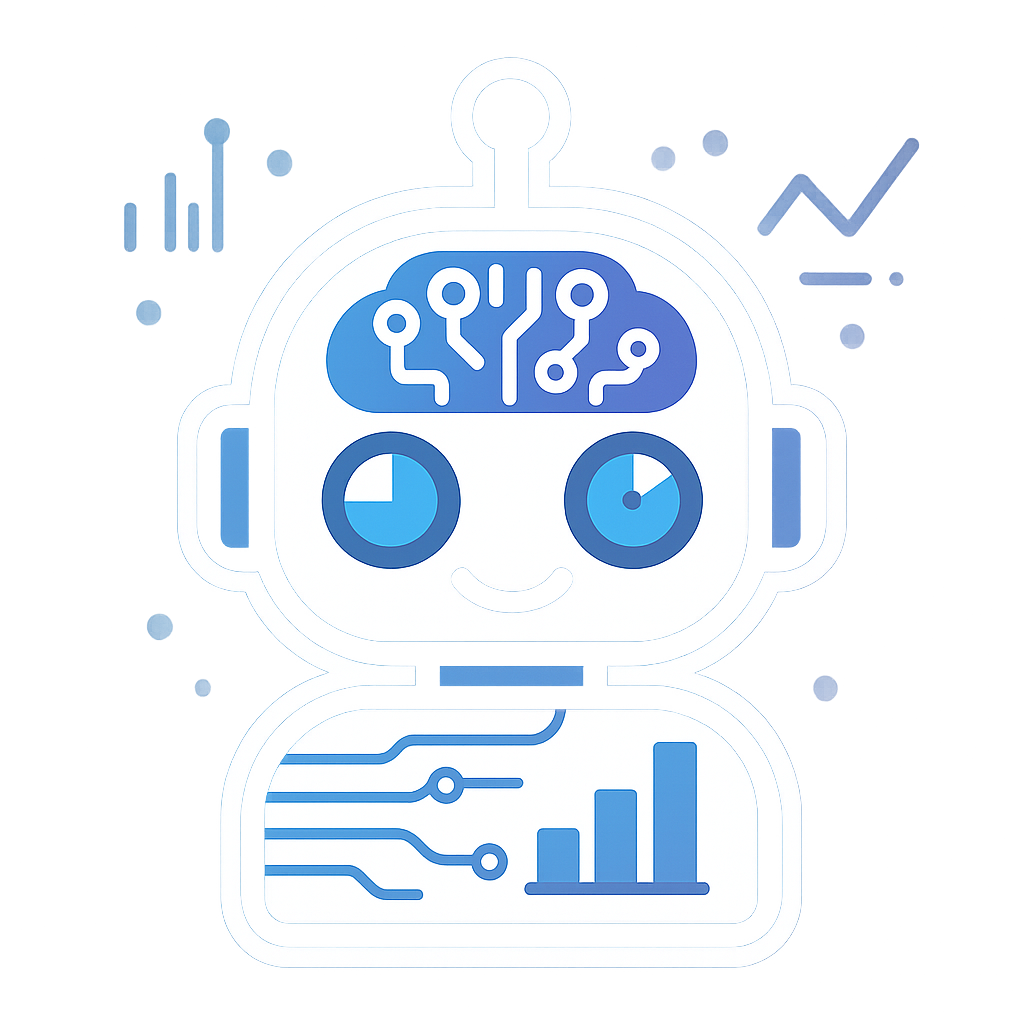生成AIの未来を読む
いま事業責任者が押さえるべき3つの視点(2025-2028)
2025年4月28日
対象:3〜4分で概要を把握したい経営層・事業責任者
技術トレンド
マルチモーダルと"分散"が主戦場
| キーポイント | 概要 | 事業インパクト |
|---|---|---|
| リアルタイム多モーダル | GPT-4o 以降、音声・画像・テキストの同時推論が標準機能化。MR/ロボティクスやCXチャネルで「待ち時間ゼロ」のUXが現実に。 | チャットボットを"目と耳を持つエージェント"へ格上げ。サポートコスト▲30%が先行企業で実証。 |
| オープンソースのプロ化 | Llama 3/Mixtral/Falcon 2 など 20–70Bパラメータ級モデルが商用ライセンスで公開。自社データで高速ファインチューニングが容易に。 | ベンダーロックインを回避しつつ、機密情報を社外に出さずにモデル運用可能。 |
| オンデバイス化 | Apple Intelligence が示したように、スマホやPCのSoC上で数十Bパラメータが動作。プライバシー保護と応答速度を同時に達成。 | "社外秘データ × AI" のハードルが一気に下がり、現場端末での自律型業務アシストが現実的に。 |
🔄
📱
🚀
ビジネスインパクト
ROIは"ワークフロー再設計"で跳ね上がる
61%
生成AI本番導入済み企業
74%
投資拡大予定のC-suite
ROIが顕著に出る条件
- プロンプト活用止まり: FAQ生成・ドキュメント作成
- アプリ組み込み: CRM/ERP 内で自動要約や文章生成
- 業務フロー再設計: AIエージェントがトリガー→承認→記録まで自動実行
経営判断のヒント
- 生成AI自体より「プロセスの見直し」を同時に行うかが分水嶺。
- OKR/KPIを"工数削減"ではなく"価値創出"で設定すると投資効果が見えやすい。
McKinsey調査: コスト-30%/納期-60%
↗
規制とリスク
EU AI Act が事実上の国際標準に
| 項目 | ポイント | 実務インパクト |
|---|---|---|
| EU AI Act | 一般用途モデルにも透明性義務。訓練データ要約・エネルギー消費報告が必須(施行:2025.08〜段階適用) | グローバル展開企業は EU 向けに開示フォーマットを追加 → "一次対応を各国子会社へ横展開"が効率的。 |
| 米国大統領令 | 安全性テストと合成メディア識別を FTC が監督(2024.10発令)。州法も分立。 | "EU型"に寄せておく方が将来コストが低い。 |
| AIリテラシー格差 | 従業員の不安・スキル不足と、規制遵守の板挟み。 | AIガバナンス担当を置き、教育+リスク管理を統合的に設計。 |
透明性義務
安全性テスト
AIガバナンス
2028年までのロードマップ
経営者向けTo-Do
1
PoCの"棚卸し"
- 部門ごとに散在するチャットボット/生成ツールを洗い出し、KPIとコストを比較。
2
AIガバナンス体制の構築
- モデル登録簿、データ使用ログ、リスク評価を一本化。
- EU AI Act 準拠フォーマットをベースに US/アジアへロールアウト。
3
業務フロー再設計ワークショップ
- RPA+生成AIを組み合わせ、「要求→承認→実行→記録」を自動化できるプロセスを選定。
- 90日以内に MVP、180日で本番移行を目安。
4
オンデバイス戦略の検討
- 社員スマホ/POS端末など現場デバイスでの AI 推論を想定し、Edge-Cloud ハイブリッドの予算枠を確保。
まとめ
- 技術面: 多モーダル化とオンデバイス化が次の競争軸。
- ビジネス面: ROIは"フロー全体の作り替え"で初めて最大化。
- 規制面: EU AI Act に合わせた透明性確保がグローバル企業のデファクト。
次の一手
経営層は 「PoC乱立→統合→業務再設計」 の3段階を設計し、AIガバナンスを経営課題に昇格させることが、2028年までに競争優位を保つ最短ルートです。